国土交通省対策サブリース被害救済措置
サブリース被害・不動産トラブル・賃貸借契約・不動産取引の経験豊かな不動産専門の弁護士に|全国の不動産専門の公務員を国土交通大学校学校で養成中
サブリース契約をこれからされようとしている方でも相談(無料)できます。
サブリースを含む賃貸住宅管理業の遵守すべきルール(賃貸住宅管理業者登録制度)ご存知ですか?アパート経営を勧誘する手口に注意ください。
サブリース被害対策は豊富なキャリアと実績に裏打ちされた不動産専門の弁護士に「今後の見通し」を不動産専門の弁護士が助言,|サブリース被害・不動産投資・アパート経営問題|不動産相続対策専門弁護士として定評がある。
サブリース被害からくる借金問題&住宅ローン返済ができずに借りてしまった借金問題|しつこい勧誘 高齢者をターゲットにする場合も

サブリース契約の前に不動産専門弁護士に相談するのが安全対策
賃料減額のリスクの説明を、どう受け止めるのか?サブリース契約の本質は、一括借り上げといっても賃料減額があり得るという現実を知ることに尽きる。
修繕費は、収益を圧迫するケースが少なくない点に注意が必要。しかも、築年数が経過して入居率が悪化してくると当然、オーナーに家賃の減額交渉をしてくる。収入が減るとオーナーは借入先の返済ができなくなるため当然のごとく反対することになる。しかしこの交渉はオーナーにとって不利になりがちだ。というのも、サブリース契約では、オーナーが貸し主となり、大東側が借り主となる。つまり借主を保護する借地借家法が適用され、オーナーよりも大東側の方が有利な立場となる。
サブリース契約の落とし穴はこの点が大きな問題点となる。だからこそ、一括借り上げのリスクとして「賃料減額」はあり得ることの認識が重要なのだ。
ご相談は、資料などをご持参ください。無料でご相談に応じますのでご安心ください。▶ CONTACT サブリース被害 お電話の場合は0120-316-018 サイムはイヤ までご連絡下さい。NHK人気番組「正直不動産」の監修をしている弁護士が直接対応いたします▶ 0120-316-018 フリー
サブリース契約は、近年賃料減額をめぐるトラブルが急増
平成30年3月27日、国土交通省と消費者庁はサブリースをめぐるトラブルについて、勧誘に関する相談・費用負担等に関する相談・家賃の減額に関する相談・サブリース会社との対応についてのご相談窓口を開設しました。■法律事務所ロイヤーズロイヤーズの弁護士竹内俊雄は、国土交通省窓口である地方整備局のエキスパートに対して国土交通大学校で指導しています。
サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受けて、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解することが大切です。
しかしこれまで寄せられているご相談内容をみると■、「家賃保証」と謳われていても、入居状況の悪化や近隣の家賃相場の下落により賃料が減額する可能性があります。また■「30年間一括借り上げ」と謳われていても、、契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約の可能性があります。さらに契約時には考えもしなかった修繕費が問題になる場合があります。オーナーにサブリース会社から修繕費用を求められるケースなどもあり、老朽化にともない建物設備の修繕費用が必要になるなど、サブリース契約をするときは、修繕費用などオーナー負担となる固定資産税もふくめ、長期目線でサブリース契約の賃料を考える必要が大切です。
今回問題となっている大東建託のトラブルは、契約までに至る勧誘にも問題点が浮き彫りに。
高齢者をターゲットに、家族を遮断し契約にこぎつける手口に被害が拡大しています。
サブリース被害の問題解決については こちらをご覧ください。 ▶サブリース被害問題解決手順 賃料返還・迅速対応
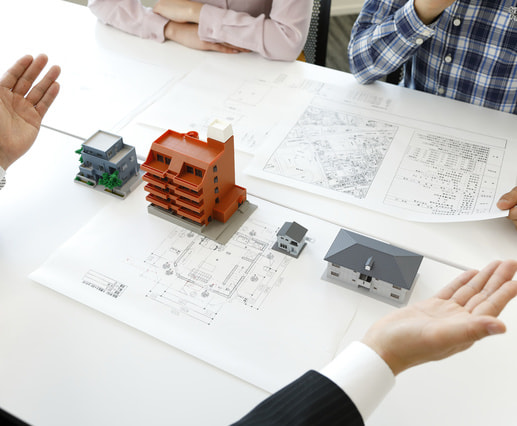
サブリース契約前の注意点
相手の業者が■賃貸住宅管理登録制度■に登録しているか確認してください。
国土交通省では、賃貸住宅管理業の適正化を図るため、平成23年から任意の登録制度として賃貸住宅管理業者登録制度を実施しています。
賃貸住宅管理業者登録制度では、サブリースを含む賃貸住宅管理業の遵守すべきルールを設けており、登録業者は、このルールを守らなければなりません。
▶あなたがマンション投資などの営業マンから、何か勧誘を受けた場合は、相手方が【賃貸住宅管理業者登録制度】に登録しているのか確かめてみることから始めてください。
契約の前にサブリースに関する登録制度の主なルールを事前にチェックすることが肝要です。
⑴重要事項の説明
サブリース契約の契約前に、将来の賃料の変動の条件等の重用事項の説明を行い、書面を交付します。重要事項の説明は、一定の実務経験者当が行うことになっています。重要な部分は「契約書」に将来の賃料の変動の条件の記載等が、どのような起債になっているか、重要事項の説明と相違はないか、また抜けてないかを確認することです。わから明確でなければ契約しないと決めて、その場で契約をしないことです。
⑵財産の分別管理
オーナーに支払う賃料について、登録業者の財産や他のオーナーの財産と明確に管理します。
⑶管理事務の報告
管理状況について、定期にオーナーに報告します。
⑷業務改善に関する勧告等
登録業者が登録制度のルールに違反した場合は、国土交通省が登録業者に対し指導、勧告、登録抹消を行います。
⑸契約書を読んでみて、賃料の変動の条件等の記載事項について心配だなと思ったら、契約をせずに専門家に相談することです。

ご相談の事例
サブリース契約にまつわる相談は、このところ急増しています
【勧誘】断っても執拗な勧誘に根負けして契約してしまった。アパートの建て替えと一括借り上げをセットにして勧誘する。
不動産会社が、マンションを建てるようにしつこく勧誘する。
勧誘の手口は、マンションやアパートを建てさせて、一括借り上げを提案することから始まります。
サブリース会社は、入居者が支払った家賃を受け取り、各種手数料を差っ引いた残りを家主(オーナー)に支払います。
当たり前のことですが、賃料が入ってこないとオーナーに入ってくる原資はありません。「入居者がいなくても家賃収入が保証されるのであれば損はないはず」と思う人が多いかもしれませんが、そんなうまい話はありません。しかし実際にそう思って契約をする人もいたので問題になりました。ニュースでも聞いたと思いますが、スマートデイズ社が提示していた賃借料は、一般のサブリース契約よりも高めの設定がなされていました。しかし、実際は、賃料不足により、一方的に賃料収入を減らされ、最後は支払われなくなってしまったのです。
スマートデイズ社だけの問題ではありません。
〇マンションの一室を賃貸するサブリース契約をしたが、十分な説明もないまま家賃収入を減額させられた。
〇サブリース契約をやめたいがやめさせてもらえない。
〇サブリース契約の更新のたびに条件が悪くなる。
〇投資目的でアパートを建てたが、サブリース会社がいなくなった。
こういったご相談に法律事務所ロイヤーズロイヤーズは解決するまで無料でご相談をお受けします。
なお、現在国土交通省では消費者ホットラインの窓口を設けて、サブリースローンがらみのご相談に対応しています。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、弁護士が消費者ホットラインの窓口である全国の地方整備局のエキスパートの養成のために国土交通大学校で指導しており、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護料をできる限り低額に抑えることで依頼者の生活の再生を図りたいと考えております。(大方の法律事務所では、着手金は、求める経済的利益の5〜8%、報酬については10〜16%)
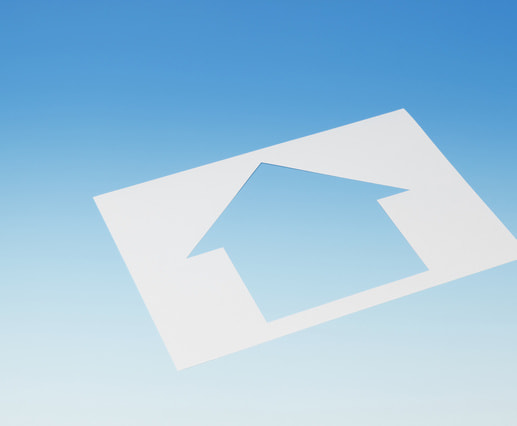
シェアハウス・投資被害
毎月多額のローンの支払いだけが残った場合
近年相次ぐサブリーストラブル、スマートデイズ社・サクト社・ゴールデンゲイン社・ガヤルド等の事業者と、スルガ銀行から高額な金利融資で、投資物件を購入された方々は、まずはご相談ください。
Aさんは、以前マンションの1室を購入するなどサブリース契約をしてお金が残るはずだったところ、更新のたびに賃料が減額され、銀行に返済する額が賃料収入でまかなえず悩んでいました。そんな時に1億円もするマンションを9000万円にするなど、一括借り上げで手元に20万円が残る話をされましたが、結局断りきれず、またもや契約してしまいました。Aさんはスルガ銀行からお金を借りて家を建てました。ところが家が建った途端、サブリース会社は別の会社に、しかも家の評価額は1000万円という価値のないものでした。スルガ銀行の査定はどのような調査に基づいた査定であったのか。
このようなケースはウソのようですが、人間の心理に潜む罠にはまった例です。サブリース契約には「賃料が入ってこなければ、安心できない」というあたりまえが、あなた任せ(サブリース会社のうたい文句を信じること)にあるところに落とし穴があるといえます。厳しいようですが、現状を打開するには、適切な法的措置が必要です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、国土交通大学校の講師でもある弁護士竹内俊雄が専門家の目線で適切な解決策を打ち出します。トラブルから1日も早く脱却できるよう支援します。
サブリース被害|被害者の声
農家や大地主さんに対して勧誘
農家の地主がアパートを建てる気になるために、行政的な後押しがあることも見逃せません。
それは以下の要因が考えられます。 1 未利用農地または将来的に利用予定のない農地がある
2 農業の跡継ぎがいない
3 相続税(改正になり相続税がアップしている)の節税ができる
4 調整区域の農地だが、アパートを建築できる条例がある 直近で相続税の増税があり大きな影響ました。
それに乗じてサブリース契約とセットのアパート建築請負契約の不動産業者の勧誘が増加したのも事実です。
資産家にサブリース契約のパンフレットを提供
2015年1月1日より改正相続税法が適用された。従来、基礎控除額は「5,000万円+法定相続人×1,000万円」であったのが、改正後は「3,000万円+法定相続人×600万円」りました。改正後は4,800万円の控除額しかなく、それを超える財産を持っている人は超える額に対して相続税が発生することになりました。
そうするとマイホームと退職金だけでも優に5,000万円を超えるケースは、今まで相続税とは無縁だったとしても改正後の今となっては相続税が発生することになります。なんと一般のサラリーマン家庭にも相続税が発生することになります。
そのために大手建築会社が力を入れだしたのが相続税対策のアパート経営・一棟建てのアパート建築です。さらにサブリース契約をセットすることで手間いれずの管理で、35年間賃料保証となると誰もが納得したつもりで契約します。
それも当然かもしれません。相続税対策と不動産は切っても切れない関係にあるからです。相続時に不動産は路線価で評価されるため、現金を持っているより不動産のほうが路線価で評価されると相続税が2割程度少なくなることになり、すなわち相続税対策に不動産は役立つのです。
通常、地価公示価格は時価を表すといわれています。路線価であれば地価公示価格の80%程度であるため、たとえば1億円の現金を持っている人がより1億円の土地が所有しているほうが、土地の価格が8,000万円で評価されるため2,000万円分資産を少なく見せることができるというわけです。 その不動産による相続税対策のなかでも賃貸アパートの経営はより相続税対策が可能になります。
たとえば相続税評価額1億円の土地と現金1億円の節税を考えた場合、現金1億円にさらに1億円を借入て2億円のアパートを建築した場合、税金はどうなるかを考えてみます。
まず、土地の評価額は貸家建付地評価となるため8,000万円程度(借地権割合を考慮すると8000万円より少しだけアップすることが考えられます)として減額される。次に建物評価額は固定資産税評価額で評価されるため、新築価格の60%程度となり2億円×60%で1.2億円程度になる。その建物には賃借人がいることによりさらに30%の借家権割合を控除できるため、1.2億円×70%=8,400万円の評価額となるります。
さらに借入金1億円も控除できるため結果として土地8,000万円+建物8,400万円-借入金1億円=6,400万円(土地の借地権を控除すると、数百万円だけ評価が上がる計算になる)の評価額となる。
すると本来あった土地1億円と現金1億円の計2億円の資産から6400万円減額の1.36億円もの相続税評価額を減額していることになり、相続税率が40%の人であれば、5,440万円(1.36億円×40%)も節税していることになります。
このようなことを現実に計算すると、以前から相続税対策にアパート経営は利用されてきたわけですが、サブリース契約の「一括借り上げ・30年間賃料保証」は相続税対策にはもってこいとして飛びつく要因になっているのです。
大手不動産業者と思って安心していたら…・
大手サブリース会社の勧誘であっても「空き室」の増加で賃料値下げが現実
テレビCMも頻繁に流れている管理会社の多くは、サブリースを事業を柱にしています。その多くは建築提携型とよばれる手法です。オーナーに対しアパートの建築を勧誘する際に「一括借り上げをして30年間家賃を保証するので管理の手間もかからない」「安心安全な資産運用」などをセールストークに、アパート建築とサブリース契約を二つ一緒に受注するケースです。こういった大手アパート建築会社は、「35年一括借り上げ」と唱ってCMにも出ているので、一見安心するのですが実際は、当初の賃料がずっと継続されるわけではありません。
大手の不動産が言うのだから安心だろうと思って、契約をしてアパートを建てますが、ひどいところはアパートが建って1か月もしない段階で、家賃を下げてもらいたい」という交渉され、揚句の果てにサブリース会社から譲渡通知が送達され、サブリース会社が変更になったと思ったとたん「中途解約」されたというケース。 酷い例では、契約の解除をちらつかせて賃料の減額を求められたり、実際に契約が解除されてしまうこともあります。
サブリース契約の注意点と対策
サブリース契約するならサブリース会社の与信能力を調査する
どうしてもサブリース会社に任せたい場合は、サブリース会社の調査をする必要があります。会社の売上・利益に占めるサブリースの割合が高すぎないか等、またサブリース会社の金融機関からの借入金額がどの程度あるのか等、サブリース会社の与信能力に充分な注意を払う必要があります。
サブリース契約の減額リスクは回避できないが…
サブリース契約の減額リスクを回避できるか?
大手不動産会社とのサブリース契約であっても、回避できないリスクの代表例が、サブリース代金の減額請求です。
判例は「最高裁では「たとえサブリース契約であっても、それが普通建物賃貸借契約である限りは、借地借家法32条1項の賃料減額請求(強行規定)が可能だ」と判示しています。つまり、家賃保証金額が経済変動などによって不相当な水準になった場合に、契約条件にかかわらず賃貸人と賃借人の双方で家賃保証金額の増減を請求する権利を認めているということです。
約条件に拘わらず貸主と借主の双方に家賃保証金額の増減を請求できる権利を認めています。私法上にどのような記載がなされていてもその条文が民法上無効であれば、その条文は当然に無効となります。
サブリースの大手不動産会社が作成したパンフレットや提案書などに「賃料は10年間見直しなしの据え置き」などと記載されているのがあります。しかし相手が大手の不動産会社だからといって記載内容をうのみにしてしまって契約したために、後になって賃料減額になり訴訟になっているケースもあります。
なお
賃料減額も中途解約もできない条文の定期借家契約を作成し、契約の締結を行えば契約期間中の減額請求リスクについては低減する事が可能です。
サブリース会社の中途解約は、法律で認められた入居者の権利
普通建物賃貸借契約の場合、「30年間保証」または「最長で35年間保証」などとうたってあってとしても、民法上、無効であるため、減額請求同様に入居者(サブリース会社)の中途解約は法律で認められた入居者の権利になります。 つまりサブリース会社から、中途解約されるリスクを抑えるためには、契約書を契約期間中は中途解約できない旨の条文を盛り込んだ「定期借家契約」とする必要があります。なおその場合は、賃料の見直しが行えない旨を記載した条文も挿入するといいでしょう。しかし、この条文を盛り込んだとしても、サブリース会社が倒産したり、行方不明になる場合もあります。リスクがなくなるわけではありません。
サブリース会社の査定賃料は適正か?
サブリース契約時の賃料保証額、つまりサブリース会社がオーナー様に毎月の支払いを約束する金額はどうやって決まるのか。 当然のことわずらわしい管理の心配はなく、サブリース会社が一括借り上げるわけであるから、その保証額はサブリース会社が査定した賃料相場(査定賃料)の85%~95%程度を家賃保証額とすることになります。
しかし、この家賃保証金額の前提となる査定家賃は、周辺の成約相場からみて「確実に入居させられる。」とサブリース会社が判断した水準となるため、通常相場以下で設定される場合が一般的です。 また、オーナー様にとって収入を抑えられてしまうという意味では、礼金などの収入や敷金などの運用益が見込めなくなるという点も着目すべき点かと思われます。 不動産をご所有される投資家・オーナー様におかれましては、サブリース会社から提示される査定賃料が、周辺の賃料相場からして適正な価格なのかどうかについて、その算出根拠について正しいといえるかどうかを注意深くご確認されることが、まずはサブリース契約の第一歩の注意点です。建てたばかりはかからなくても修繕費は年数が経つほどかかってきます。賃料は建てたときのスタート時点で、周辺のアパートには空き室がないのか、賃料はいくらくらいなのかを自分の目で確かめてみることが大事です。
サブリース契約と、マンション(アパート)建築は同時がベスト
土地の金額を投資金額に含めずに収支計算を行うのであれば,「建築予定の賃貸マンション(アパート)の収支計画に記載された想定収入」から「土地を駐車場等で貸した場合に見込む事ができる収入」から差し引いた金額が、賃貸マンション(アパート)を建築する事によって生み出される収入である事を見込み建築(投資)の有無を決定すべきです。不動産建築業者は建築を受注する(建築請負による利益を上げる)ため、一般相場と比べ高いサブリース賃料を提示します。そうでないとお客様が投資しようという気持ちにならないからです。サブリース賃料も高い金額で提案し,一方で建築価格も通常より高い金額(初期投資額が過大)になってしまう為、結局は儲からない不動産投資になってしまうケースが殆どです。固定資産税の評価額を見てがっくりというケースは少なくありません。
また、大手ハウスメーカーやゼネコンなどの建築業者は、建築後10年、20年経過した際に修繕費や、回収建築費として名前が通っているだけに高額な提示をしてきます。意外に回収金額は高額になるものです。
どうしてもサブリース契約を前提にお考えであれば、建築の発注前にサブリース契約書の内容チェックを済まし、建築発注とサブリース契約の締結を同時に検討・確認すべきです。
維持管理費用は資産価値を下げないために必要
通常、サブリース契約を結んだ場合、建物の維持管理に掛かる費用はサブリース会社の負担で行う事が一般的です。そこでサブリース会社の収益を考えてみると、【サブリース会社の利益】=入居者からの賃料収入-(所有者へ支払う保証家賃+維持管理費用)」となるので、サブリース会社は、入居者からの賃料収入が大きく下がってしまわない程度に維持管理費用を削減します。
。維持管理費の削減は、不動産投資・不動産経営において非常に大事なポイントですが削減した結果どうなるかです。サブリース期間中に維持管理費を抑えられすぎた為にサブリース契約終了後の維持管理費が大きくなり、資産価値(売却価格)が大きく下がってしまっては投資どころか赤字になりかねません。修繕費はそれなりに必要です。そのためサブリース契約を結ぶときは、メンテナンスといったことも含め考えなければなりません。維持管理や修繕計画の立案だけでもビルメンテナンス専門の業者のアドバイスを受けるとか、併せて専門のメンテナンス業者と別途ご契約されるといったことも必要です。
サブリース会社とのトラブル|対策
サブリース業者の不当な契約解除・減額交渉にはすぐに応じない
弁護士に依頼(調停・損害賠償)することをお勧めします
サブリース会社の勧誘方法の問題点
「30年間賃料保証」はサブリース会社のうたい文句。
「オーナー様は何もしなくても管理はお任せください」となると誰もが、わずらわしい手間がなく安定した賃料が保証されるなら、しかもサブリース会社は大手だからと安心しても無理からぬこと。
ともかく、30年間賃料が安定的に変わらずに入金されるという錯覚を起こさせ事業計画が安定したものであることを計画書などを提示されて契約をしてしまうことがあります。
しかし年々老朽化が進むのは間違いなく、老朽化に伴い修繕費がかかることになります。したがって、新築同様の収益は続かないということです。
ところが、勧誘の内容を聞くと、収益が右肩上がりの曲線で示されている事業計画を見せられたという実態が浮かびあがってきます。当然そのような事業計画はあり得ないのです。
このようなあり得ない事業計画を提供し、アパートを建築させたというのであれば、問題があります。
サブリース会社のうたい文句で、アパート建築をする場合、アパート建築請負契約を締結する条件でサブリース契約をする場合がほとんどです。通常は、アパートを建築するとなると、少しでも安く、いい材料で頑丈な建物になるように気を配るものです。老朽化が進まないように塗装などにも気を遣い細かく注意を払うでしょう。
ですが30年間も長期にわたり、一括借り上げてくれると思うと、注意もそれほど払わず建築会社におまかせするようになり割高になってしまっている現状が現場で生じています。
ここからが問題です
サブリース被害は、被害に気付くことが遅くなるということです。
それは、サブリース契約の賃料が滞るようになりようやく気付くからです。場合によってはアパートの竣工から何年もしないと被害にあったと気づきにくいことがあります。賃料の減額を迫られたり、賃料が滞ったりして初めて被害にあったと気がつくからです。そうなると銀行返済がサブリース業者から支払われる賃料頼みになってしまっていることから、サブリース会社から契約を解除された場合は、たちまちローンの返済ができなくなることから賃料減額に応じてしまい収益どころか修繕費を考え合わせると赤字という結果になります。
アパート建築請負契約をしたが途中で解約できるかという問題ですが、サブリース会社の勧誘に問題がある場合は、取り消しの主張ができます。早い段階であれば特定商品取引法のクーリング・オフを行使することもあり得ます。取り消したいという場合も、建築に入る前か建築途中なのか、また勧誘に問題がない場合でも取り消すことは可能です。一定の金額(違約金)を支払えば契約は取り消すことは可能です。
○減額交渉に対する対処法
判例によると(東京高等裁判所平成15年(ネ)第5399号建物賃料改定等本訴請求、収入保証額確認等反訴請求控訴事件 平成16年12月22日判決)
最高裁判所の裁判例は、「一定期間の賃料保証を約し,被控訴人においてこの賃料保証等を前提とする収支予測の下に多額の銀行融資を受けてビルを建築した上で締結されたサブリース契約であることからすれば,上記鑑定額をもって直ちに本件の相当賃料額であるということはできない。本件における相当賃料額を決定するに当たっては,賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合考慮すべきであり,特に本件においては,上記の賃料保証特約の存在や保証賃料額が決定された事情を考慮しなければならず,とりわけ,被控訴人が本件の事業を行うに当たって考慮した予想収支,それに基づく建築資金の返済計画をできるだけ損なわないよう配慮して相当賃料額を決定しなければならないというべきである。」また、これを受けた高等裁判所では、サブリース契約締結時の家賃保証の約束と収支予想を尊重するべきだとし、周辺の賃料相場にあわせるべきとして賃料減額請求を行ったサブリース業者の請求をほぼ認めなかった判断もなされています。
○サブリース会社の不当な契約解除・解約への対処法
いきなりの解除は、オーナーにとってローンの返済があるだけに相当な痛みを伴うことになります。それをわかって「賃料減額に応じなければ契約を解除する」と、強硬に要求してきます。こういった場合は、すぐに応じることなく弁護士に相談することをお勧めします。解除が無効だと主張するとか、損害賠償を検討するとか調停に持ち込むとか、安易に応じないことです。
・初期段階 訪問販売による契約|特定商取引法 クーリング・オフ
最近目立つのは不動産業者によるサブリース契約にともなうアパート建築請負契約の勧誘です。
不動産サブリースに関するアパート建築請負契約は、不動産業者などが訪問して勧誘がなされるなど、訪問による勧誘や契約がなされることがあります。いわゆる訪問販売です。訪問販売は、事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事です。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
サブリース契約にともなうアパート建築請負契約の勧誘も、特定商取引法が適用されないか検討する価値があります。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売(「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと)等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。訪問販売や電話勧誘販売など、問題の起こりやすい商法を規制する法律ですが、無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」を定めている法律でもあります。
住宅建設会社様の展示場や店舗で請負契約を締結する場合は、 訪問販売には該当しないためクーリング・オフの適用除外になります。訪問販売といっても、ホテルの一室であったり、レストランや取引銀網などは全て取引販売の対象になります。不動産業者の事務所と認められず、類似とも認められません。
特定商取引法の改正がなされ、建築請負契約も同法の対象です。同法は、「営業のためにもしくは営業として」契約する場合には適用されない、という規定もおいていますが、何もよく分からないままに、図面などを見せられて一棟目のアパートの建築契約を締結させられたなどの場合には、クーリング・オフできる可能性は十分あります。
また、同法は、虚偽の説明または、不当な勧誘をした業者を取り締まる規定も置いています。納得しないままの契約、または勧誘があったと思われたら、まずはクーリング・オフの申し入れをすることです。押し切られるようであれば迷わず不動産専門の弁護士か消費者庁に相談することです。
不動産の賃貸借に関わる増減請求|借地借家法32条1項
判決文に引用された法律「借地借家法32条1項」の条文を抜粋して掲載しました。ちらっと見てください。判決文がわかりやすく感じてくれるといいですが‥‥。
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
不動産・サブリース関係に関する判例は、こちらをご覧ください。 ▶サブリース被害 判例



















